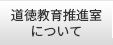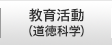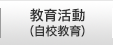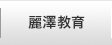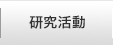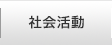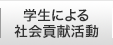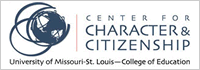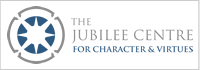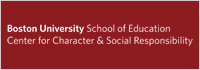社会活動
ボストン大と麗澤大が共催でサーヴィス・ラーニングについてのシンポジュームをボストン大で開催
 去る9月24日から27日にかけてボストン大学を訪問した。今回の訪問の目的は二つある。一つは、26日に開催された本学とボストン大学共催のシンポジューム(CCSR Kevin Ryan Symposium:Service Learning Strengthening Character Across Cultures: Japan and the United States)でプレゼンテーションをすること。もう一つはボストン大と締結した学術協定に関する覚書(MOU)を更新することである。
去る9月24日から27日にかけてボストン大学を訪問した。今回の訪問の目的は二つある。一つは、26日に開催された本学とボストン大学共催のシンポジューム(CCSR Kevin Ryan Symposium:Service Learning Strengthening Character Across Cultures: Japan and the United States)でプレゼンテーションをすること。もう一つはボストン大と締結した学術協定に関する覚書(MOU)を更新することである。
 MOUの更新はシンポジューム当日の午後2時半より、ボストン大の学長室で行われた。プロヴォ―スト(学務担当の最高責任者)であるジーン・モリソン氏は、すでに2011年にお会いしているので、2年ぶりの再会である。日光が降り注ぐ学長室の窓からは、滔々と流れるチャールズ川が一望に見渡せ、終始和やかな雰囲気で両校のさらなる学術的・教育的交流を確認し合った。
話は前後するが、ボストン到着当日は、時差ボケを解消するため、ハーバード大学の生協であるハーバード・クープに向かった。ここではハーバード大グッズだけでなく、大量の書籍も販売されている。3階の「哲学」のコーナーへ行ってみると、本学とボストン大との共同執筆本が販売されていた。それも立てて横並びになっているのではなく、購買者の注意を引くように表紙が見えるように陳列されている。旅の疲れも吹っ飛んだ一コマだった。
MOUの更新はシンポジューム当日の午後2時半より、ボストン大の学長室で行われた。プロヴォ―スト(学務担当の最高責任者)であるジーン・モリソン氏は、すでに2011年にお会いしているので、2年ぶりの再会である。日光が降り注ぐ学長室の窓からは、滔々と流れるチャールズ川が一望に見渡せ、終始和やかな雰囲気で両校のさらなる学術的・教育的交流を確認し合った。
話は前後するが、ボストン到着当日は、時差ボケを解消するため、ハーバード大学の生協であるハーバード・クープに向かった。ここではハーバード大グッズだけでなく、大量の書籍も販売されている。3階の「哲学」のコーナーへ行ってみると、本学とボストン大との共同執筆本が販売されていた。それも立てて横並びになっているのではなく、購買者の注意を引くように表紙が見えるように陳列されている。旅の疲れも吹っ飛んだ一コマだった。
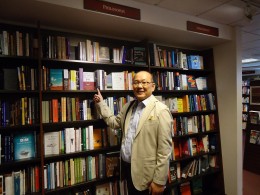

私はシンポジューム後に帰国したが、水野教授と古川氏はその後もアメリカ各地で精力的に学術交流の日程をこなしてきた。 以下は水野修次郎教授のレポートである。 ボストン大学教育学部「人格と社会責任センター」でライアンシンポジューム開催 9月26日(木)ボストン大学教育学部にて「サービスラーニングによる諸文化における人格の強化」というテーマでシンポジュームが開催されました。麗澤大学の中山理学長は、このシンポジューム開催に当たり、麗澤大学とボストン大学との研究交流の歴史と今後の課題について発表があり、ロゴス(理論)、パトス(情動)、エートス(心的態度・道徳的規範)のすべてに品性を発達する教育の必要性が訴えられました。
 ピーター・ラフ教授からは、「日本とアメリカとの比較」について発表があり、文化による違いを比較するだけでなくて、異なる文化を結ぶ努力をする必要があるとしました。
発表者の古川範和道徳科学研究員は、「日本におけるサービスラーニング―内側からの展望」について話し、自分の経験より麗澤大学やモラロジー専攻塾での学習体験について紹介がありました。
水野修次郎麗澤大学教授は、「道徳教育のインパクト」と題して発表し、道徳科学教育センターとミズーリ大学「人格と市民性センター」との共同研究でもある道徳教育効果の測定についての研究についての中間発表がありました。
ピーター・ラフ教授からは、「日本とアメリカとの比較」について発表があり、文化による違いを比較するだけでなくて、異なる文化を結ぶ努力をする必要があるとしました。
発表者の古川範和道徳科学研究員は、「日本におけるサービスラーニング―内側からの展望」について話し、自分の経験より麗澤大学やモラロジー専攻塾での学習体験について紹介がありました。
水野修次郎麗澤大学教授は、「道徳教育のインパクト」と題して発表し、道徳科学教育センターとミズーリ大学「人格と市民性センター」との共同研究でもある道徳教育効果の測定についての研究についての中間発表がありました。 ボストン大学からは、スコット・サイダー准教授から「サービスラーニングと人格の向上」について、フィリップ・テイト教授からは「犠牲」についてのコメントがあり、主体的に奉仕をするその人のアイデンティティについて議論を展開しました。その後、センター長のエレンウッド教授の司会による活発な質疑応答が展開されました。
今回のシンポジュームの意義は、道徳は体験的に積極的に実践することによって学習できるという確信を得たことです。さらに、サービスラーニングは人格の向上に大きなインパクトがあるという共通理解を得ました。今後の発展が望めるテーマでもあるので、継続研究が必要です。
ボストン大学からは、スコット・サイダー准教授から「サービスラーニングと人格の向上」について、フィリップ・テイト教授からは「犠牲」についてのコメントがあり、主体的に奉仕をするその人のアイデンティティについて議論を展開しました。その後、センター長のエレンウッド教授の司会による活発な質疑応答が展開されました。
今回のシンポジュームの意義は、道徳は体験的に積極的に実践することによって学習できるという確信を得たことです。さらに、サービスラーニングは人格の向上に大きなインパクトがあるという共通理解を得ました。今後の発展が望めるテーマでもあるので、継続研究が必要です。 9月27日には、水野教授と古川研究員はカーボンデールの南イリノイ大学を訪問しました。南イリノイ大学では、教育学部の教職職員と学長から歓迎の言葉をいただき、麗澤大学との交流に興味について積極的な発言がありました。水野教授は、「ゆるすことと日本文化」という講演をし、日本文化の特色である「自己に反省し品性を向上させる」ことと西 洋文化でいう「ゆるし」についての関係について紹介しました。会場からは西洋社会ではあまり議論がされていない「反省」についての質問が多くありました。
9月27日には、水野教授と古川研究員はカーボンデールの南イリノイ大学を訪問しました。南イリノイ大学では、教育学部の教職職員と学長から歓迎の言葉をいただき、麗澤大学との交流に興味について積極的な発言がありました。水野教授は、「ゆるすことと日本文化」という講演をし、日本文化の特色である「自己に反省し品性を向上させる」ことと西 洋文化でいう「ゆるし」についての関係について紹介しました。会場からは西洋社会ではあまり議論がされていない「反省」についての質問が多くありました。
 9月29日には、水野教授と古川研究員は、ミズーリ大学にある「人格と市民性センター」を訪問し、開発中の道徳教育インパクト測定について議論を進めてきました。道徳教育の影響を測定することは、たいへん難しい研究ですが、当センターのマービン・バーコビッツ教授、ジュリー・キャップ博士(評価や測定の専門教授)、メリンダ・ビア博士(研究科学者)との話し合いで、まずは今までの道徳教育によってどのようなインパクトが在学生、卒業生にあったのなのかを調査することから始めることで同意しました。さらに、選択した徳目(慈愛、責任、肯定的人生、感謝、つながり・相互依存、尊重、反省)の理論的な定義とそれらの測定にすでに開発されている測定具の調査をすすめることになりました。
9月29日の午前中には、バーコビッツ教授の提案でプリンシピア大学を見学しました。同大学の先生二名バーコビッツ先生指導の下に博士論文を作成中という関係もあって、見学が実現しました。プリンシピア大学は、メアリ・ベーカー(Mary Baker Eddy 、1821-1910)によって提唱されたクリスチャンサイエンスという宗教の下に創建された大学です。広大な敷地に600名ほどの学生が勉強していました。学生と教職員はすべてクリスチャンサイエンスを信仰しています。この大学で学ぶ者は、病を信仰で治療した経験を持つ人たちです。この大学での話し合いで、病は、品性の向上によって治癒されるという廣池博士の考え方を紹介したところ、数名の教員が強い関心を示しました。
9月29日には、水野教授と古川研究員は、ミズーリ大学にある「人格と市民性センター」を訪問し、開発中の道徳教育インパクト測定について議論を進めてきました。道徳教育の影響を測定することは、たいへん難しい研究ですが、当センターのマービン・バーコビッツ教授、ジュリー・キャップ博士(評価や測定の専門教授)、メリンダ・ビア博士(研究科学者)との話し合いで、まずは今までの道徳教育によってどのようなインパクトが在学生、卒業生にあったのなのかを調査することから始めることで同意しました。さらに、選択した徳目(慈愛、責任、肯定的人生、感謝、つながり・相互依存、尊重、反省)の理論的な定義とそれらの測定にすでに開発されている測定具の調査をすすめることになりました。
9月29日の午前中には、バーコビッツ教授の提案でプリンシピア大学を見学しました。同大学の先生二名バーコビッツ先生指導の下に博士論文を作成中という関係もあって、見学が実現しました。プリンシピア大学は、メアリ・ベーカー(Mary Baker Eddy 、1821-1910)によって提唱されたクリスチャンサイエンスという宗教の下に創建された大学です。広大な敷地に600名ほどの学生が勉強していました。学生と教職員はすべてクリスチャンサイエンスを信仰しています。この大学で学ぶ者は、病を信仰で治療した経験を持つ人たちです。この大学での話し合いで、病は、品性の向上によって治癒されるという廣池博士の考え方を紹介したところ、数名の教員が強い関心を示しました。 文責 水野修次郎
文責 水野修次郎